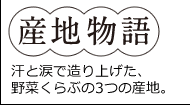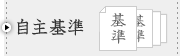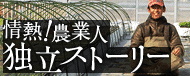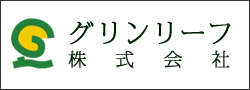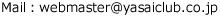野菜くらぶを作った、3人の男たち。
その生い立ちと栽培の苦労、野菜作りへの想い。
汗を流す3少年…赤城山の中腹と山麓で

1972年夏、標高750メートルの赤城山、昭和村糸井、大河原地区。南は浅間山から榛名山、北には新潟との県境にある谷川岳から尾瀬の燧ヶ岳(ひうちがたけ)まで見渡せる高原で、1人の少年が雑草と格闘していました。照りつける太陽の下、高く茂ったトウモロコシ畑の中には高原の風も届かず、息苦しいほどの暑さ。全身から噴きだした汗で、とうにシャツはびしょ濡れです。少年は小学6年、野菜くらぶ設立メンバーの一人、林美之(みゆき)です。
同じ頃、林家から少し下った標高700メートルの久呂保(くろほ)地区では、男の子が小さなからだを精いっぱい伸ばして、トラクターを運転していました。澤浦彰治、当時小学2年です。離農された土地を購入し、澤浦家が現在の野菜くらぶの場所に移住してきたのは、ちょうどこの10年前。妹3人を持つ長男として生まれた澤浦は家業をよく手伝い、小学4年になると「全部自分がやるから、豚を飼おうと」と、一人で養豚を始めるほどの熱の入れようでした。
そして赤城山麓の畑では、アスパラ畑の雑草を抜き終わった竹内功二が、母親が冷やしておいてくれたスイカにかぶりついていました。姉3人の末っ子として生まれた竹内の家は、標高300メートルの利根川沿いで、同じ久呂保でも比較的暖かな地区。露地イチゴやトマトなどを栽培していた両親は、朝早くから夜遅くまで働き、竹内も当然のように農作業を手伝っていました。澤浦とは同級生で気が合い、遊びに行っては澤浦宅に泊まることもしばしばだったといいます。
林美之、澤浦彰治、竹内功二。この3人が野菜くらぶを設立するのは、この時から20年後のことです。でもその話は、のちほど。もう少し、3人の足跡をたどってみましょう。
葉っぱがしおれる根こぶ病に、将来を憂う日々


林家は祖父の時代にこの地を開墾し、やや下にあった生越部落から移住。姉と弟を持つ長男として生まれた林も、家業をよく手伝う少年でした。「祖父は頭の切れる働き者で、値段のいいじゃがいもや馬鈴薯の種芋を作って、一代でここを築きました。厳しくて、子供の頃はよく柱に縛りつけられたものです」。まだ潅漑(かんがい)施設の整っていなかった赤城山麓では、そばや麦、陸稲(おかぼ、または、りくとう。畑で栽培する稲)が主食。「もっちり感がないので、おにぎりにすると一口でバラバラになりましたね」。父親の代になって白菜、大根などの根菜類、のちにレタスを作り、自ら高崎の市場に運んで生計を立てていました。
中学を卒業した林は、地元の農業高校に進みます。「高校時代は農業クラブ(笑い)」と言うほど農作業を手伝い、「日曜はたっぷり手伝うので、月曜は昼を食べたら寝てましたね。でも母親が連絡帳に書いてくれたのか、教師は何も言わなかった」。卒業して、両親とともに農業を始めました。
林が現実の厳しさを思い知らされたのは、このときでした。市場に持って行くと、レタス1ケースに100~200円という値段しかつかないこともあり、しかも売価をその場で知ることはできません。林は「なぜ自分で値段がつけられないのか」という、当然の疑問を持つようになります。「それからの10年間が、いちばん悩みが大きかったかもしれませんね」。そうした悩みを抱えながらも、農村青年たちの組織、農業青年クラブ協議会(通称4Hクラブ※)で試験栽培などの活動に力を注ぎ、約600名もの群馬県組織の会長を務めるようになります。
しかし、畑には異変が起きていました。根こぶ病が発生していたのです。根こぶ病とは白菜などのアブラナ科の野菜に発生するもので、根っこがコブ状になり水分を吸いにくくなる病気。「白菜、キャベツ、ブロッコリーなどの葉っぱが、気温の上がる日中しおれてしまい、夕方涼しくなると元気になる。ずっと化学肥料で作っていたためと、
 すばらしい夕焼けが見られます
連作障害でしょうね。このまま行ったら何も作れなくなるのではないかと、危機感を持ちました」。ちょうどその頃、父親が60歳を機に引退を決意し、林は家業を受け継ぐことに。30歳になっていました。
すばらしい夕焼けが見られます
連作障害でしょうね。このまま行ったら何も作れなくなるのではないかと、危機感を持ちました」。ちょうどその頃、父親が60歳を機に引退を決意し、林は家業を受け継ぐことに。30歳になっていました。
養豚研修を終えて家に入り、たい肥運搬用のダンプを買ってもらう


その頃昭和村は、バブルに沸いていました。昭和村の主な産業は酪農と野菜栽培、特にこんにゃくの生産量は日本一。さらにこの頃は、早朝収穫した野菜をその日のうちに都市部に届ける朝採り野菜が人気を呼び、農家の所得は増える一方という状況でした。
そんな中、林が高校を卒業するのと入れ違いに、澤浦と竹内が、林と同じ高校に入学してきました。澤浦はここで、重量挙げに出合います。来る日も来る日も練習を重ね、高校3年でインターハイ4位、国体少年の部で6位入賞という成績を上げて、無事卒業。その後、県の畜産試験場の研修過程で畜産を学んだり、ハム加工の方向を探ったりしました。
研修を終えて家業を手伝うことになった澤浦は、景気もよく農家を継ぐ条件に高級車を与えるという農家が多い中で、「車が欲しいから家を継いだと思われるのがイヤで、たい肥運搬用のダンプカーを買ってもらった」といいます。家業のかたわら澤浦も、林同様、農業青年クラブ協議会に入り、会長を務めています。
しかし平成に入り、バブルの崩壊とともにこんにゃくも野菜も価格が暴落して、澤浦家はピンチに。「もう人任せにはできないと思いましたね。

毎年の収穫祭も、大にぎわい!
それでどうしようかと思ったときに、目の前にあるこんにゃくを加工して売れば、何とかなるかもしれないと思ったのです」。こんにゃく加工を始めたのは、野菜くらぶ設立の1年前、1991年でした。
外を見に、長野県野辺山へ。最先端のレタス作りを学ぶ


一方竹内の高校時代は、家の手伝いとアルバイトに明け暮れていました。「親父は、金はくれられないけど時間はくれると言ってくれた。それで米の集荷とかこんにゃく芋の洗いなんかのバイトをして、バイクを買った」。高校には3ない運動(バイクに「乗らない」「買わない」「(免許を)取らない」)というのがありましたから、ちょっとやんちゃです。でも近所で乗り回すようなことはせず、新潟に出たり北海道に行ったり。「バイトや旅行で人生観変わりましたね。将来は外に出ようと思うようになった」。このとき竹内と行動に共にしたのは林の弟。林ともアルバイト先で共に働いたことがありました。
高校卒業前にちょっとした事故を起こした竹内は、「『外の飯を食ってこい』と先生に言われて」、卒業と同時に長野県の野辺山高原に研修に行くことに。しかし本当は、水耕栽培を学びたかったと言います。「そのころ霜や台風で大きな被害が出たんです。水耕栽培だったら、天候に左右されずに安定した収穫が得られますからね」。研修先が見つからず断念しましたが、しかし野辺山はレタス栽培のメッカ。そこでの経験は、その後の野菜くらぶにとって幸いしました。懸命に働いた研修先では仕事を任され、トラクターの免許まで取らせてもらい、大型機械を使う当時の最先端農業を体験。しかしそうして帰ってきた竹内にとって手作業による農業はなじめず、父親とよくぶつかったと言います。
「バブルの時は、すごかったよ。野菜は腐ったら売れないけど、腐っても売れるのがこんにゃくだと言われていた。

仕事を待つ作業着。ハウス内は暖か
それで全部の畑をこんにゃくにしようとした。ところが植え替えたとたん、バブルが崩壊した」。こんにゃく一本では食べていけなくなり、無農薬こんにゃくも手がけながら白菜やレタスを作り、冬はスキー場にアルバイトに出るようになりました。
「実はさ、作るのは大変なんだけど、無農薬の契約栽培やる気ある?」

1992年の秋口、農業青年クラブのことで、澤浦が林のもとを訪れました。作業小屋でキャベツの箱詰めをしていた林に、澤浦がこう問いかけました。「これ、いくらくらいで売れるんですか?」「まあ、1箱500円がいいところかな」「実は、作るのは大変なんだけど、契約栽培やる気ある?」「どんなの?」「無農薬なんだけど」「無農薬か…やったことないな」
澤浦はこんにゃくの無農薬栽培を始め、手作りこんにゃくの売り上げも順調に伸びていました。そんな時、売り先のひとつだった「らでぃっしゅぼーや」さんから、「無農薬こんにゃくができるなら、野菜も無農薬でできないか」という話をもらいました。聞いてみればとても澤浦1人でできる注文量ではなく、高校時代の友人など10人に声を掛け、説明会を予定しました。しかし説明会当日、集まったのは林、竹内、澤浦、そして宮田徳彦さんの4人だけ。宮田さんは今は野菜くらぶのメンバーですが、すでにお客さんを持っていたためこの時は辞退しました。
ここに創立メンバー3人がそろい、この年の10月、有機野菜生産グループ「昭和野菜くらぶ」が誕生しました。それにしても、今まで使っていた薬を使わずに、注文通りに野菜を出荷することができるのか。この日から、3人の闘いが始まりました。
(続く)
※4Hはhead、hand、heart、healthの頭文字。地域での交流、親睦、農業技術の改良などを目的とする農村青年の組織。1960年ころから衰退。
●トップの写真は、林の畑付近から(10年1月撮影)